🔹IPOシリーズ【2025年10月16日上場】テクセンドフォトマスク(429A) 【後編】 再び注目される親子上場
前編【👉前編はこちら:https://note.com/dejire/n/n635458293dde?app_launch=false】では、フォトマスク市場の拡大とテクセンドフォトマスクの技術的背景を整理した。後編の本稿では、同社の上場構造を通じて「親子上場」「PEファンド設計」「資本効率改革」という3つの視点から、近年のIPOの潮流を読み解く。
TOPPANホールディングスとインテグラルが組成した本案件は、日本企業の上場モデルがどう変わりつつあるかを示す分かりやすい一例でもある。
10. 再び注目される親子上場 ― 資本効率化とガバナンスの再定義
今回のIPOは、いわゆる親子上場型の上場である。親子上場は2000年代中盤、海外アクティビストから少数株主の利益を損なうとの批判を受けたのち、東証も縮減を後押ししてきた。ピーク時(2006年度末)の417社から、2022年度末には約200社まで半減している。
しかし2023年以降、親子上場は再び増加に転じている。大企業がグループ内事業を部分的に切り出すカーブアウト型上場の増加しているためだ。
この動きの背景はまず第一に、東証の市場再編と上場維持基準の厳格化がある。プライム市場では流通株比率や時価総額などの基準が明確化され、PBRが1倍を下回る企業には、資本を有効活用していないとの厳しい視線が向けられるようになった。資産を持っているだけではダメで、それをどう株主価値に転換するが問われる時代になった。
この環境変化は、親会社にとっても眠っている資産を市場で活かす動機づけとなった。子会社を上場させることで、グループ全体のROE改善につながるうえ、支配権を維持しながら配当を得ることもできる。いわば、リスクを抑えつつ果実を得る道を見出した。
TOPPANホールディングスの場合、フォトマスク事業のように高ROICを誇る優良事業を抱えながらも、多角化による資本の重さがグループ全体のROEを押し下げる要因となっていた。同事業を独立上場させることで、成長力を市場に可視化し、かつ、グループ資本の効率性を高めることができる。
またフォトマスクのような重投資型産業においては、長期的な取引関係の移管や資本構造の転換が容易ではなく、完全なスピンオフによる即時独立は現実的でないといった状況もあっただろう。
11. PEファンド参入から上場までの経緯
今回のIPOは、上場プロセスの制度設計に豊富な実績を持つPEファンド、インテグラルをパートナーに迎え、当初から上場を出口として描いたエクイティ・カーブアウトであった。
TOPPANホールディングスは2022年、フォトマスク事業を独立採算型へ移行させるため、インテグラルとの共同出資によってトッパンフォトマスク株式会社を設立。設立時点での資本金は約380億円、そのうちインテグラルが約180億円を出資(出資比率49.9%)し、共同事業体制が構築された。その後2年間で上場に向けた整備を進めたのち、2024年に社名をテクセンドフォトマスク株式会社へ変更。今回の上場へと至る。
12. IPOの特徴
IPOは売出中心型であり、主な目的はPEファンドであるインテグラルによる部分的なイグジットであった。売出株式数は約3,261万株、新規発行株式数は700万株と会社への新規資金流入は全体の2割弱。
上場後の株主構成は、TOPPANホールディングスが約50.1%、インテグラル関連ファンドが約35%前後。TOPPANホールディングスは長期的な保有継続を示唆しており、フリーフロート比率は全体の2割未満。
公募価格は3,000円で、上場時の時価総額は約910億円、吸収金額は約1,150億円規模となった。バリュエーション面では、公募価格(3,000円)・予想EPS(約220円)ベースでPER約13.6倍。業界平均と比較しても割高感はない。
また、今回のIPOは海外売出比率が約56%と高水準であった点には注意を払っておきたい。海外機関投資家の積極的な需要が初値形成を押し上げた一方、中長期ではEUVや先端半導体関連銘柄としてのテーマ性を背景に、安定保有主体による需給の下支えが期待される。
株主還元においては2025/03期で1株あたり90円の配当を予定。キャッシュフローの安定性を背景とした配当余力の高さがうかがえる。
13. 3年で2.8倍のリターンを得たインテグラル
インテグラルは2022年、トッパンホールディングスからのフォトマスク事業分割に際し、約180億円を出資して49.9%の株式を取得。当初の純資産は約380億円だったが、事業譲渡などの再編を経て1年後には純資産が約490億円へ増加。この時点でインテグラルには約110億円相当の含み益が発生し、持分評価額(全体の49.9%分)は約500億円規模に達していた。
今回のIPOでは、その保有分の約半分(=テクセンド全体の約25%分)を売却。公募価格3,000円ベースで約80億円を回収。出資時点からの総リターンは約320億円(投資額比約2.8倍)に相当し、残るテクセンド全体の約25%分(時価約250億円)を引き続き保有している。
14. 変化するIPO市場とPE主導の台頭
上場審査が厳格化する近年、IPO市場では、上場準備を制度的に整えられるPEファンド主導の案件が増えている。かつてPEファンドは、企業再編や不採算事業の整理を担う裏方の存在だったが、現在は上場を前提に設計する上場請負人としての性格を強めつつある。
その一方で、一か八かで挑むVC主導のスタートアップIPOは東証市場で減少傾向にある。上場維持基準の厳格化に加え、上場後のIR対応や監査・ガバナンス体制の維持に多大なコストがかかる上、株価が伸び悩むケースも多く、上場=成功という従来の価値観が見直されつつある。その結果、スタートアップ側も無理に上場を目指さず、非上場のまま資金を循環させる仕組みの制度設計が進められており、上場に依存しない資金調達の動きが強まってきているようだ。
リスクマネーはより安定した収益基盤を持つ企業へとシフトしつつある。
以上
【免責事項】
本レポートは投資勧誘や特定の金融商品の売買推奨を目的とするものではありません。記載内容は信頼できる情報に基づいていますが、その正確性や完全性を保証するものではなく、将来の見通しも作成時点の判断にすぎません。本レポートに基づく投資判断はすべて利用者ご自身の責任で行ってください。なお、本レポートの著作権は筆者に帰属し、無断での複製・転載・引用は禁じます。掲載・引用を希望される場合は、事前に筆者の許可を得てください。
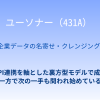
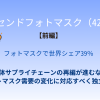
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません